『四月は君の嘘』連載インタビュー
![]()
アニメ『四月は君の嘘』に関わるスタッフのリレーインタビュー。
第9回目は新川直司先生の最初の担当編集である、江田慎一さん。
新川先生の漫画の魅力について、
そして『四月は君の嘘』の誕生秘話を語っていただきました。
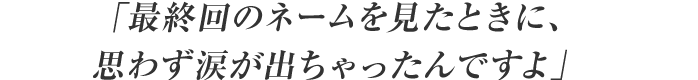
新川先生が『四月は君の嘘』に挑むまで
――『四月は君の嘘』の漫画家・新川直司先生と江田さんはデビュー以来ずっとお仕事をしてきたそうですね。お二人の出会いは何がきっかけだったのでしょうか?
彼(新川先生)が新人賞に応募してきて、僕はその応募作がおもしろかったので担当を希望したんです。そこから二人三脚でやってきました。新人漫画家がデビューするには、まず新人賞に2~3作応募して、できれば大賞や入選を獲るという階段の上り方があるんです。彼は4作目の新人賞で準入選を獲ったので、それで新人賞は卒業。次は連載を狙おうという話になりました。
――最初の新人賞のとき、新川先生の作品の印象はどうでしたか?
応募作はファンタジーめいた話だったんです。剣をもった主人公がいろいろな敵をぶった切るというストーリーでした。はっきり言ってしまうと、絵はそれほど上手くなかった。構成も今ほど洗練されていなかった。でも、とてもいい1コマがあったんです。すべてが終った後、主人公が壁に寄りかかって剣を抱えて座り込んでいる。たぶん魂はもう彼の体を離れているのですが、その顔がなんだかとても幸せそうに見えたんです。その絵の印象がすごく強く残っていて、ああ、この人(新川先生)はすごく良いなと。それで声をかけたんです。

――そこからずっとごいっしょされてきたんですね。
そうですね。新人賞のあとにはじめたのが連載狙いの『さよならフットボール』の原型のネームでした。単行本一冊分くらいのネームができあがった、まさにその時、山野(史郎・新川先生のもうひとりの担当編集)が、辻村深月先生の『冷たい校舎の時は止まる』をもってきたんです。彼は小説好きなので、その作品を「漫画化できる人いないかなあ」と探していたんですね。そこで「新川さんはどうだろう」と話をしたんです。辻村先生に彼の描いたコンテを見てもらったところ、幸いにも気に入っていただいて、そこから山野と新川さんの3人タッグで『冷たい校舎の時は止まる』の連載が始まりました。この作品は講談社文庫(全2巻)にもなっていますのでぜひ読んでみてください。
『冷たい校舎』の完結後、当時の増刊「イーノ」で『さよならフットボール』をはじめました。原型のネームはサッカーに特化した話だったんですが、もう少しふくらませて日常シーンをいろいろと入れて単行本2巻分にしたんです。僕が言うのもなんですが、『さよならフットボール』は傑作です。14歳のサッカー少女が、同級生の男の子に混じってたった1試合だけピッチに立つ。煎じ詰めるとそれだけの話なんですが、さまざまな障害や体格差を乗り越え、最後には敵さえ魅了してしまう彼女の戦いぶりは、個人的に『君嘘』の演奏シーンにさえ匹敵すると思っています。10月に新装版(全2巻)で出ましたので、新川先生ファンは必読ですよ(笑)。そして次がいよいよ『四月は君の嘘』です。

――そこから『君嘘』につながるわけですね。
実は『君嘘』のネタは、もともと新川先生が新人のころからもっていたんです。最初の新人賞で奨励賞を取ってから次に持ってきた何本かのネタの中に、ヴァイオリンを弾く女の子の話があったんです。『君嘘』とはちょっと違って、男の子も女の子もヴァイオリニストでした。ただ、僕は学生のころに音楽の現場をかじっていたので、「これはもうちょっと絵が上達しないと難しいな」と思っていました。新川先生が、このインタビューシリーズの中で「ボツになった」といっているけれど、ボツにした僕自身、今の形でそのネームが復活するとは夢にも思っていませんでした(笑)。
――江田さんの経験がそういう判断を生んだんですね。江田さんはどのように音楽に関わっていたんでしょうか?
中学校のころはブラスバンドでトランペットを吹いていて、高校生のときはオーケストラでヴァイオリンを3年間、合唱もやっていました。大学ではミュージカルサークルに入っていましたね。だから、音楽にずっと関わってきたんです。

――江田さんが音楽の漫画に関わったことは?
『BECK』の担当の一人でした。
――それは失礼いたしました! 『BECK』はまさに音楽漫画の代表格ですね。漫画で音楽を描くうえで、ひとつのスタイルをつくりあげた作品です。
そうですね。音が出ない漫画上での楽器の音や声の表現に、著者のハロルド作石さんは相当こだわっていらっしゃいました。『BECK』の主人公のコユキの声が(漫画だから)どんな声かわからない。その部分を大事にされていたんです。新川先生も『BECK』の大ファンみたいですし、そのあたりで音楽の表現は影響を受けているのかもしれませんね。
――新川先生もロックがお好きだそうですね。
そうみたいですね。連載当初は、新川先生にクラシックの世界をより深く知っていだたくためにいろいろな取材をしました。もちろんコンクールも行きましたよ。実際のコンクールは漫画の中みたいに「わーっ」とはならない。地区予選なんか客席は身内ばかりだし、シーンとしていて咳をするのもはばかれるような雰囲気でした。課題曲が3曲ぐらいあって、その中から1曲を選んで演奏するんだけど、たいてい同じ曲をずっと聴くことになるんです。でも、その中でも演奏の雰囲気が全然違う子がたまにいて。宮園かをりみたいな子も実際にいるんですよ。すごいなあと身を乗り出して聴いていたら、その子と目線が合うんですよ。「私を見て」って言っているような気がして、びっくりしました。その子は本選上位に行くんじゃないかなと思ってたら、残念ながら最終結果には名前はありませんでしたけど。

――そういう取材を重ねて『君嘘』に挑んだわけですね。
ピアニストやヴァイオリニスト、音楽家のみなさんと食事をして音楽界の内輪話をいろいろと伺ったりもしました。
――有馬公生の「ピアノの音が聴こえなくなる」という題材はその取材の中から生まれてきたものだったんでしょうか?
あれは新川先生のオリジナルのアイデアですね。でも、音楽家の方に聞くと似たようなことが起きるらしい。集中しすぎると、音が自分が出しているものに思えなくなって、まるで他人が弾いているように聴こえるって。実は僕も中学のころ発表会へ出たときに公生と同じような経験があるんです。トランペットを独奏するパートで、僕のトランペットの音が鳴らなくて……。
――ええっ!
「あっ! 音がでない!!」と判ったときの心境は今でも覚えていますよ。自分の心がすーっと静まり返ったんです。宙を浮いて漂っているような感覚があって、「ここにいる自分は自分じゃない」と思っているうちにそのパートが終わっちゃった。そのときの会場の匂いや雰囲気もよく覚えています。

――その音が出なかった理由は何だったんですか?
うーん。技量の未熟さに加え、過度の緊張もあったんでしょうね。練習ではトチッたことないのに、本番では音が出なかった。途中から音が出てもカッコ悪いなと思って、結局そのパートは音を出せませんでした。終わった後、同級生や指揮の先生から何も責められず、逆につらかった記憶があります。かをりみたいな子に「アゲイン」と言ってもらったら、その後の人生も変わっていたかもしれません。

新川先生の素顔と作品が生まれる瞬間
――『君嘘』における2人の担当編集者、江田さんと山野さんの役割分担ってどうなっているんでしょうか。
役割は特に決まっていません。漫画家にとって編集者というのは、最初の読者なんです。年齢も趣味も得意分野も異なる複数の編集者が、極端に言えばそのネームがおもしろいかおもしろくないか、話がわかるかわからないか、と漫画家と打合せするわけです。少年誌は若い読者を相手にするわけですから、たくさんの視点があったほうがいいんです。そのジャンルに詳しくないほうが素直に批評できる場合もある。だから、「月刊少年マガジン」はたいてい複数担当制です。そうは言っても、山野に原稿の入稿や単行本の編集作業をやってもらっているので、仕事量は彼のほうが多いのですが。
―――『四月は君の嘘』のネーム(構図、下書き)作成はスムーズに進んだのでしょうか?
最初は1話目が2つに分かれていたんです。でも編集長の要請もあって、どうせなら第1話と第2話を一気にやろうと。物語の導入もいろいろと考えながらいまのかたちに落ち着きました『冷たい校舎』のころは原作に準拠しつつ漫画的な構成にしなければいけないので、かなりやりとりしましたし「ここのシーン全部削ろうよ」みたいな話もしました。でも、そういう経験を経たうえで『君嘘』に取り組んでいるので、大きな問題は何もありませんでした。音楽的な表現の問題もほとんどなかったです。一回だけですね、ネームをボツにしたのは。でも新川さんは次の日に全てを書き直して持ってきたんです。びっくりしました。今では、私も山野も新川先生の世界観、透明感を最大限活かそうと考えながら仕事をしています。ちなみに、彼新川先生はネームを歩きながら考えるらしいです。いまはどうかわからないですけど、『君嘘』の最初のころは、外を歩きながらやっていたようです。電話を掛けると、たいていどこかを歩いているんですよ(笑)。良いシーンや良いセリフを思いつくために刺激を与えているんじゃないかな。独特のリズム感もそこから出ているのかもしれないなと勝手に想像しているんですけどね。

――新川先生との打ち合わせのときはどんな雰囲気なんですか?
ネームができたらコピーを2人分取って、それを山野と私で読んで「今回もいいね」と、新川先生に感想をお伝えします。だいたい「いいね」としか言うことないんですが(笑)。そのあと、少しだけサッカーの話などの雑談をするんです。先生は四六時中作品のことを考えているタイプなので、いっしょにメシを食べるときぐらいはバカな話をして息抜きをしています。
――新川先生は漫画に打ち込んでいる方なんですね。
真摯に打ち込んでいらっしゃるので、原稿も早いんです。新川先生は自分なりに締め切りを設けていて、本来の締切よりも2週間以上早く仕上げてくださるんです。しかも、そのサイクルをきっちりと守っている。編集者としては極めてありがたい方です(笑)。
――公生タイプなのかも。
そうかもしれません。ただ先生は、三池君に一番感情移入していると言っていましたね。三池君は表現者として頑張ったり、突っ張ったり、弱かったり……すごくあがいているじゃないですか。そこが「自分に似ている」と言っていましたね。

新川先生と江田さんが目指しているもの
―――『四月は君の嘘』のアニメ化のお話が来たときはどんな印象でしたか。
最初にアニプレックスの斎藤(俊輔/プロデューサー)さんが相談に来たときは「1クールで」という話だったんです。その時点で漫画のラストのイメージは決まっていて、そこから伏線を張り巡らせてつくっている話だったので、途中までアニメ化されるのは困るなと。それで最初はお断りしたんです。そうしたら、しばらくして斎藤さんがあらためてやってきて「2クールで」と。それでならぜひお願いしますということになりました。アニプレックスさんだし、A-1 Picturesだし、ノイタミナだし……座組みには文句はありませんでしたね。
―――実際にアニメをご覧になっていかがでしたか?
いやあ、第4話を拝見して感動しました。僕は『四月は君の嘘』本編に登場する曲を……1曲につき何百回も聴いているんですが、アニメでは演奏がズレるところなどをしっかりと描いていて本当にすばらしいなと。やはり原作ファンの方々は、演奏シーンをどのように映像化しているかが気になっていたと思うんです。でも、その期待を裏切らない、すばらしい映像化でした。

――今回、現在連載中の原作漫画の最終回までアニメ化するという、同時進行の作品になっていますね。この試みについて、原作漫画側ではどうお考えでしたか?
斎藤さんをはじめ『四月は君の嘘』に関わっている方全員が、作品に対して愛をもってくださるのが伝わってきて本当にうれしかったし、熱意に応えるために原作側もできるだけ協力しようと考えました。斎藤さんから「同じタイミングでアニメと漫画のクライマックスを迎えたい」というアイデアをいただいて、こちらも「ナイスアイディア!」と引き受けてしまったんですが、新川先生には、ほんと無茶振りを受けていただいて感謝しています。
――江田さんは、新川先生とお仕事をはじめて10年近くになるわけですね。あらためて、新川先生とはどんな作家であると思いますか?
今思うと、当時から世界観ができあがっている人だなと思いましたね。新人賞に出した作品の2本目も、3本目も全然違う題材なんだけど同じテーマを描いていたという印象があります。おそらく、そういう意味では『四月は君の嘘』もまた、新川先生の描こうとしているテーマをまっすぐ描いている作品と言えると思います。新川先生は『四月は君の嘘』を描く上で、いっさい妥協しないんです。絵を描く上では、音楽はとくにごまかそうとすればできちゃうんだけど、ヴァイオリンの演奏も持ち方や指がどこを押さえているかも含めて絶対に逃げない。ストーリー上でも、母親の死からも逃げないし、病気やトラウマからも逃げない。すべての登場人物が前向きに立ち向かうというのがこの作品の特徴になっていると思います。
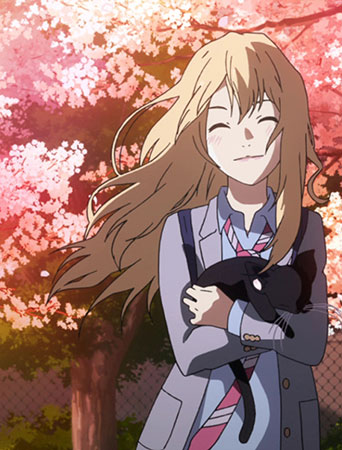
―――なるほど! その逃げない描き口に僕らは感動するのかもしれません。
これは笑い話なんですが、新川先生は大分前から「江田さんをいつか漫画で絶対泣かせる」とおっしゃっていたんです。先日……最終回のネームを見たとき、編集部で周りに人がいるのに、涙をこらえるのが大変でした。最後の最後に、新川さんにやられてしまったなあと思いましたね(笑)。

次回(11月20日予定)は、馬場高知さん(エピックレコードジャパン(音楽協力))のインタビューを公開します。
お楽しみに!
